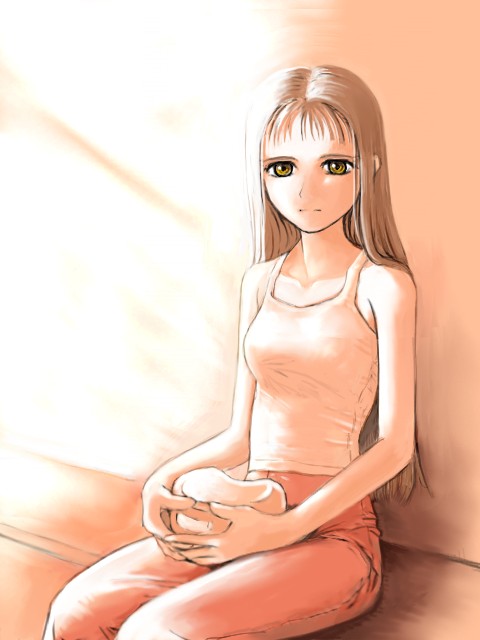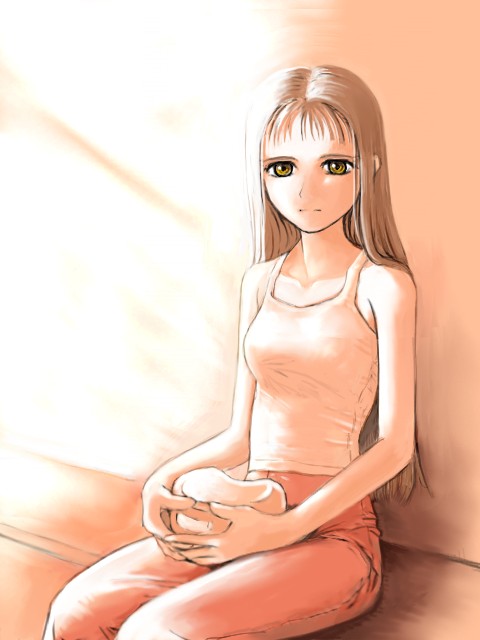ハマのカメラ
first impact
(write 2002.07.01)
(update 2006.05.24)
「ロボットの開発で、一番うまくいかなかったのは『感情』を持たせることでした」
ふくよかな老婦人が、カップをゆらしながら静かに語る。ココネは身を乗り出すようにして、彼女の話に聴き入った。
「身体の機能は、ほぼ人間に近いものを用意できたし、理論上は感情らしきものをもたせることもできたはずなんです。でも初期のロボットには、ついに感情は生まれなかった。・・・人間そっくりな今の貴女を見ていると、とても不思議です」
ココネは、すこしだけ照れたようにうつむいた。制服のタイが揺れる。
「わたしたちの頃には、もうこれが当たり前になっていましたから・・・」
彼女がいま相対しているのは、アルファシリーズのかなり初期の頃、その開発に携わったという人物である。
ムサシノ運送の荷物鞄に入っているのは、この老婦人が、かつて育てたというロボットの遺品だった。
ココネ自らが希望したこの配達先は、人里を遠く離れたところに、人目を避けるようにして建っていた。
運送会社の制服で訪ねてきた愛くるしいロボットを茶席に招き、控えめなココネの質問に応えて、老婦人は語る。
訥々(とつとつ)と、表情を緩ませながら語られるのは、ハマと名付けられた女性ロボットのことだった。
ロボット開発の歴史において最終期といえる時代、現在のアルファ型の基礎となるモデルが作られたのは、地震や暴風、海抜の上昇や気温の変動など、異常気象が次第に激化しはじめた頃のことだった。
この頃のロボットは、外見においてはほぼ完全な基準で人間を模すことに成功し、定期的なメンテナンスこそ必要だったが、およそ自律的に機能する、一個の疑似生命体と言えた。
ただ、現在のアルファ型と大きく異なる点があった。このときの実験体であるハマには、全くと言っていいほど表情というものがなかったのだ。
ハマは、命令されたことをただ実直に施行する。極端に的はずれなことはしないが、融通が利かないところがあり、また語彙もきわめて少なく、自分から話をすることはほとんどなかった。
空を見て何か感じるかと問われれば「青いです」と言い、海を見ても「青いです」と応える。研究所の敷地から臨めるものに対しては、何を見せても万事この調子だった。ハマには、温度や触覚、味覚なども感覚器から入力でき、その情報も脳器官で認識されるという、人間そっくりの仕様が実現している。なのに、彼女の出力だけが、ひどく淡泊だった。
あるとき、ハマが大怪我をしたことがあった。どこかで転倒したらしく、ひじあたりの皮膚がべろりとめくれている。痛覚はあるはずなのに「すこし痺れがあります」と、ハマは、やはり他人事のように言った。
ハマが若かった老婦人の自宅へ来たのは、実用化へ向けての実習のためである。
記録用のカメラと、わずかな衣服袋だけを持って連れられてきたハマを、開発機関の研究所職員として忙しかった彼女は、在宅勤務への切替を条件に、しぶしぶながら受け入れた。
彼女には、死に別れた夫との間に、そのとき12才になる一人娘がいた。しっかりした娘で、家にまで仕事を持ち込んで没頭する彼女に代わり、その娘が家事家計を切り盛りしていたほどだ。最終的に、ハマの居候を誰より喜んだのはこの娘である。実直なハマは、教唆、指示された仕事は一発で覚えたからだ。仕事内容は、おもに家政婦のそれだったが、研究に明け暮れる彼女と、それを支える娘の生活に、ハマは大いに役立ってくれた。ハマは命令を下す娘のことを、誰から吹き込まれたのか「お嬢様」と呼び、娘に付き従った。
しかし、ハマとの暮らしがはじまってしばらくたったころ、娘は死んでしまった。異常気象による河川の増水にまきこまれ、溺れたのだ。ハマがそれを救おうとしてくれたが、婦人がふたたび会えた娘の姿は、泥にまみれてハマが抱きかかえてきた死体だった。
娘が死んでからしばらくの間、婦人は、ただ虚脱して、ぼうっと日々を過ごしていた。その間もハマは、決められた仕事をこなすように、黙々と彼女の世話をしつづけた。
それからすぐに、定期検査の命令があった。河に飛び込んだハマのメンテナンスの意味もあるのだろう。しかしハマは、研究所への帰還指示を断った。
驚いたのは研究者である。ハマの発言には、それまでなかった明確な「自主的な意志」があったのだ。
研究者は機材を搬入し、婦人の家で検査をおこなうことで、ハマを納得させた。それまで理論上は存在してしかるべきなのに、どうしても見いだせなかった「感情」らしきものが、やっと芽生えた環境を、できるだけ大切にしたのだろう。
しかし、このときの検査では、何も結果らしいものはでなかった。ハマの脳器官からは、とりたてて数値的な変化は検出されなかった。
そのころの世界は、異常気象による、慢性的な食糧難に見舞われていた。
ロボットが食事によって自らエネルギーを生み出し、メンテナンスフリーとなるシステムは、このときすでに確立されていた。それに必要な食料はごく少量だったのだが、それでも「食い扶持をへらせ」という、ロボットへの不当な排斥の気運が世の中にはあった。
社会不安がそうさせたのだろう。ハマの兄や姉にあたるロボットへの不当な虐待がひんぱんに報じられ、おそらく、それに数倍する暗数の暴力が、陰でロボットを襲ったことだろう。あるものは破壊され、晒(さら)しものにされる事件もあった。
娘の死からどれくらいたっただろう。
いつからか婦人は、ハマのことを、娘と同様に愛そうと思うようになった。それは自分への慰めだったのかも知れない。だが、このことは、ハマを与(あずか)った自分の使命なのだと思う。
成人女性ほどの体格のハマを、胸にかき抱いて眠ったり、世話係の娘が死んでから、ずっと荒れ放題だったハマの髪を、毎日のように、一房ずつ丁寧に梳(と)かす。研究所の仕事を放り出して、婦人は彼女の面倒をみるようになった。しかし、当のハマは、相変わらず無表情で、なんの反応もなかった。
あるとき婦人は、研究所へ一度かえることをハマに薦めた。
ハマは、気がつくと、こちらをじっと見ていたり、首を傾げたまま静止していることが多くなった。かと思うと不意にとんとんと小さくジャンプしたり、とつぜん写真を撮りだすなど、理解に苦しむ行動が目立つようになった。彼女はそれを不思議と気味悪くは思わなかったが、なにかの障害がではじめているのかもしれないと心配になったのだ。
一度、精密な検査を受けておいた方がいいだろう。
そう薦めると、ながいながい沈黙のあとで、ハマはようやく「わかりました」と言った。
ハマはその翌日に、なんの表情もない顔で形式どおりの別れを告げ、カメラとごく簡単な荷物をもって研究所へ帰った。
それが、婦人がハマを見た最後の姿だった。
研究所での検査が始まって何日かすると、ハマは何度も帰宅希望を申請したらしい。このときの検査は異常に長引いたようで、実際に数ヶ月にわたっていた。帰還指示を拒否したとき同様、ハマの訴えは研究者を驚かせもしたが、この間に、結局それは叶えられなかった。
後の報告によれば、帰宅申請が却下されたハマは、研究所をひそかに抜け出したのではないだろうか、と言われている。
研究所の建物から、ほんの100メートルほどのところで、ロボット開発に反対していたグループにより、ハマが破壊されるという事件が発生したのだ。それは、満足な形も残らないほどの、酷い死に様だったという話だった。
「そんなことがあったんですよ」
彼女は、何も見ていないような目で、何十年も昔の話に、もう己のこころがざわつかないことを、確認していた。
「このことがあってから、わたしは研究機関を辞しました。だからどう研究が進んだのかはわからないけど、それからしばらくして、感情を持つロボットが生まれるようになったのよ。」
ココネは、以前に別の人物から聞いた「ハードな過程」の一端を垣間見たように思っていた。書籍や一般向けの記録媒体に残されていない、リアルな歴史である。
その証拠品が、いまココネのカバンの中にあった。ハマの遺品となったカメラが、さいきん逝去した研究所員の荷物から見つかり、運送を依頼されたのである。手配は、研究所員の遺族がおこなったらしい。ココネはそれを説明し、老婦人の前にそっと箱を差し出した。
「なつかしいわ・・・」
開梱して、表面がうすく褪色したカメラを撫でながら、彼女は目を細めた。現在でまわっているロボット用のカメラとは違い、その本体はとても大きい。だが、原理的な部分は同じように思えた。ファインダーもモニターもやはり無く、いくつものコードをつなぐジャックだけが、露出している。
「でも、いまここには再生する端末がないんです。もし良かったら、あなた見てくれないかしら。それで、あの子がどんな写真を見ていたのか話してくれませんか」
老婦人の申し出を、ココネは、興奮を隠して丁寧に受けた。彼女自身も、初期のロボットの記録を見てみたかったのだ。
カメラは古い型だが、規格は問題ない。電源を投入し、コードのボール端子をくわえ、ココネはボタンをクリックした。
一枚目が脳裏に浮かぶ。
これは、ロボットの顔だろうか。
およそ表情というものがまるで無い、冷徹な印象すら受ける少女の顔がこちらを見ている。
ハマの写真だろう。話に聞いたとおりの印象だと、ココネは思った。
最初は、自分で自分を撮ったのかと思ったが違うようだ。撮影者の主観情報がなにもない。撮影時の空気感や、ときにはそのときの感情までもが擦り込まれるこの種のカメラ独特の情報がないのだ。ビジュアル以外の情報が皆無で、ただの無味乾燥な触感の画像が、脳裏に現れている。背景がこの家の玄関ということは、撮影者はこの老婦人だろうか。
「ハマさんが写っています。たぶん、あなたが撮影されたものですね。」
二枚目。なんの気もなくクリックしたココネは、突然爆発したような勢いで再生された圧倒的な情報量に、一瞬、あたまの中身を全部ふっとばされた。
自分の目の前に、両手をこちらに伸ばして顔を隠している婦人がいる。
首をすくめて、撮影を照れているようなまだ若い婦人を、いままさに自分が撮影しようとしていた。
たまらなく幸せな、踊るような嬉しさがこみ上げてきて、我知らず、ぴょんぴょんと飛び跳ねたくなる。
これが静止画像だということを認識するまでに、コンマ数秒の時間がかかった。まぶたを開くと同時に、強烈に引き戻される感覚が脳を押す。しかし、肉眼を開いていてなお、現実かと見まごうばかりのリアルな視感覚が、その画像データにはあった。
それは、老婦人を撮影した写真だった。このすさまじい情報量。撮影者は、まちがいなくロボットだ。おそらくハマだろう。ココネは、呆然とした。
初期型の性能だろうか。撮影者の主観と、そのときの心情が、そのまま、まともに画像データに焼き込まれていた。
「タイムマシンのようなものだと思う」
かつて、同類のロボットが、この手のカメラを評して話していたことを思い出す。
このカメラに記録されるのは、ヴィジュアルとしての情報だけではない。
撮影者のあらゆる主観が記録されるのだ。この記録を通じて、ハマのすべてを体験することができるのだと、画像を送りながら、ココネは悟った。
しかし、それにしても聞いた話とずいぶん違う。ハマの中には、こんなにも激しい「感情」があるではないか。それに、老婦人から聞いた「いつも無表情だった」という話とは、これもずいぶん違う。これはまるで仲のいい親子のような親密さだ。
疑問に思いながらも、ココネは写真を繰る。
婦人が居眠りしているところを、となりの部屋からこっそり撮った、絵のような一枚。
家事をする後ろ姿をとらえた写真は、窓からの逆光で婦人自身が光って見えた。
たまに、婦人とハマが一緒に写った写真もはさまっていたが、いくつもの記録キューブにおさめられた膨大な量の写真のほとんどが、かつての老婦人を撮影したものだった。
そして、そのどれにも、強烈なほどの慕情が染みついている。
ココネには、クリックをする指が止められなかった。カメラから伝わる感情が、侵略する奔流のように流れ込んでくるのを抑えられなかった。二枚目以降の報告をしなくては、と思っているのに、彼女は、飢えたように写真を見送っていった。この写真は、撮影者の感情を丸呑みしている。その全ての情報が、ココネの内部に次々と染み込んでいく。一枚目のあの無表情な撮影者が、嬉しくて仕方がないといった風情で記録をとっていたことが、我が事のように思えた。懐旧に近い歓喜。それがココネを捕らえ、離そうとしない。
しかし、あるときから、データの質が一変する。
日付データによれば、この家での最後の一日に集中的に撮られたスナップは、偏執狂的なほど、なんでもないありきたりなカットの老婦人を捕らえ続けていた。ほぼ同じアングルで、撮影時間も一秒ほども変わってない。ほとんど消去していいような連続写真。でも、その全てが強烈な切なさに泣いていた。
自分は、このひとと別れなければならない。
自分は、ここを離れて生まれた場所にもどるように言われた。彼女が命じるのなら、わたしは断ることができない。
検査が終われば帰ることが出来るとは思う。でも、すこしでも離れていることが辛い。
その別離の苦しみ。真っ二つに引き裂かれる苦痛に、撮り続けられた写真は、すさまじく歪んでいた。
研究所にもどったハマは、婦人に会いに行ける日を、どれほど恋いこがれたのだろうか。
撮影したときの喜びに満ちた、錯覚なのかこちらの胸まで熱くなるような画像データが、なんどもなんども繰り返し再生され、そのときにわずかづつ上書きされ擦り込まれた再生者の思慕の情が、変色などするはずのないこの画像を、かすかににじませている。
検査にしっかり応えて、充分なデータを出力できたら、すぐにでも帰ろう。時間がかかるようなら、一日だけでも帰らせてもらおう。
そんな決意までが伝わってくるように感じた。
ほどなく、食糧難の時勢で、ロボット開発をすることに反対するグループの活動が盛んになり、外出自体が禁じられた。手紙などの伝達手段も、この時期にあった大地震で寸断されている。
ココネの胸に去来する、はげしい焦りの感情は、そのせいなのか。
寂しさと、老婦人の身を案じる想いが、身を切られるような切実さで、自身の中に再生されていた。
この想いはどうして、届くことを許されなかったのだろう。
そう思ったとき、ココネはハマになった。
ココネは悔しさに似た悲しみとともに、カメラの中で、ハマとして存在していた。
ハマの最も深層にある古い記憶に手が届く。何度も思い出し、リフレインしたのだろう、その記憶だけが異常なほど鮮明だった。
頬を打つものすごい量の雨。激しい泥流から上がったばかりの自分。そして腕の中にいる少女。その子が囁くように言う。
「おかあさんを助けてあげて」
ほんのちいさな、しかしこれが、ハマの記憶とよべる、原初のものだった。
婦人の姿が浮かぶ。
あのときから、私はお嬢様のかわりにあなたを助け、支えようと思ったのです。
この気持ちは、はじめて持つ私の宝でした。あらゆることを感じられるのに、なにも「思うことができない」私の精神領域に、はじめて直接進入してきたコマンド。落ちてきた種。それは遺命ではありましたが、脳器官に命令言語で与えられたコマンドではなく、私のこころに、はじめてとどいた指令です。
この宝石のような命令のために、私はあなたを助け、お支えしようと思いました。でもそれは最初だけのことでした。
写真の映像が繰り返しよみがえる。
いつしか、あなたが私を娘のように愛してくださった事実が、わたしの中に水のように注がれたのです。
お嬢様から受け取った感情に芽が生え、大きな樹のようになっていくのを、わたしはそのとき理解しました。
わたしはあなたに娘のように愛されて、はじめて「こころ」を得ることができたのです。
でも私にはそれを表現するプログラムがなかった。言語にしようと思っても満足な語彙を持たず、なんと表現していいかわからなかったのです。こころばかりがはしゃぎ回るのに、それを表すことができない。でも。それでもいい。いまはただ、あなたにもう一度だけ会いたい。お会いして、時間はかかるかも知れないけど、このことを全て報告したい。そう思っておりました。
言葉が、ココネの口からあふれ出そうとした。
いつのまにか、カメラとの接続は切れていた。しゃくりをあげて泣きながら、必死に言葉をつなごうとするココネ。しかし、なにも頭にうかばない。どうしてもこの気持ちが言語に変換できない。
ココネの表情をみていた老婦人が、何かに思い当たったように、ハッとする。
そして頬に手をあてつぶやいた。
「・・・そう。そうなのね」
目を上げるココネ。老婦人の目からは、静かに涙が流れていた。
それを見たココネの中で、轟々と渦を巻くように荒れていた感情が、不意に柔和な花のようになった。
何もかもが。このときをまっていた全ての時間。一分も一秒までも。濃密な想いが流れ出ていく。かわりに注がれる蜜のような愛情に満ちた微笑み。その心情の全てが完結される充実感。
ハマがそうしたかったように、ココネが老婦人にそっと抱きつく。
ハマにそうしてきたように、老婦人はココネの髪をなでて、つぶやくように言った。
「おかえりなさい」
ココネは吊られていた糸が切れたように、その場で崩れ落ちた。
動かなくなってしまったココネを、彼女は胸にかき抱いた。
そして、やさしく、ココネの髪をひとふさずつ、撫でていった。
紅茶のカップを、ソーサーに置く。
落ち着くまでに、時間がかかった。
わけもなく、生理機能で泣いた後のような感覚だけが残っている。
自分がなぜあんなにも激しく泣いていたのか、ココネにはもうわからない。
でもとてもスッキリした。いまは、自分だけの気持ちで、ものを考えられていると思う。
カメラに残っていた狂おしいほどの情熱は、すでに消えていた。
かすかに、高ぶった感情の残滓がある。
人前で、あんなに泣いたことが、妙に気恥ずかしい。
愛想笑いなど出そうになるのを抑え、ココネは丁寧に失礼を詫び、家を退出した。
老婦人は無言で、迎えとの合流場所まで歩くココネを見つめる。
地震や洪水で夫と娘を失って、ハマまでいなくなって、この広い家に、また、わたし一人だけが残る。
でも、それでもこうして生きていけるのは、思い出があるからではありません。
あなたたちが、いるから。
カメラに添えられていた手書きのメモを、老婦人がもういちど読み返す。
メモには、H.A.M-A7M0号基・ハマが研究所に帰還したことで、ロボットの開発は、ひとつの段階を突破したことが書かれていた。さまざまな検査の末、成長した感情素子ともいうべきものが、彼女の中に発見されていたのだ。
それ以降、ロボットはハマを祖とし、感情をもつ存在としてあたらしく出発した。
何度もなんどもふりかえり、手を振っては去っていくココネを見ながら、老婦人は唇だけでつぶやいた。
あなたたちは、私の娘なのよ。
夕風が彼女の肩を撫でる。
もう、ココネの姿は見えなくなっていた。