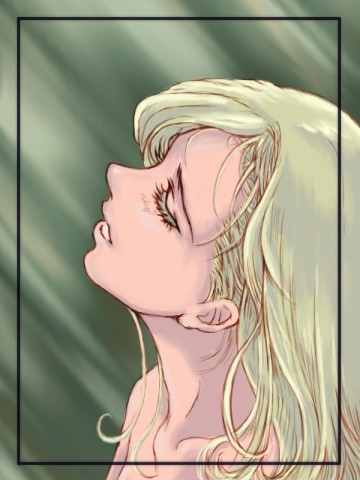
孤高の信仰者
prayer
(2004.04.01 upload)
(2004.04.10 finished)
孤高の信仰者
prayer
(2004.04.01 upload)
(2004.04.10 finished)
序
「なんだ、そんなことを悩んでいたの?」
「マリア様がみてる」の9巻目にあたる「チェリーブロッサム」において、藤堂志摩子がそれまで思い悩んでいた秘密があきらかにされる。
志摩子の実家が仏教の寺であること、なのに娘の志摩子はカトリックに憧れシスターになる夢をもっていること、それがいつか両親をはじめとする誰かに迷惑をかけるかもしれないこと、だからそれが知られることとなったら、自主退学を考えていること。これが、藤堂志摩子が背負っていた心の闇「秘密」である。
「マリア様がみてる」が世に出たのは、1997年2月発行の「月刊コバルト」誌上に公表された、先述の「チェリーブロッサム」が最初だ。
その後、時代をさかのぼって文庫本として仕切なおし、無印の1巻目がでたわけだが、文庫版「チェリーブロッサム」に時間軸がおいつくまでの間、志摩子の秘密は思わせぶりにもったいつけながら明かされないできた。
それだけに、読者の多くは「なんだ、そんなことを悩んでいたの?」と事実に対して拍子抜けだったと思う。作者もあとがきで、本人にとっては重大事というようなフォローをしているが、それでも志摩子がここまで離さずひとりで持ち続けてきた事態の重さと「そんなこと」の間にはおおきなバランスの差がある。なにか重要なファクターが欠けているようで、これがどうにも腑に落ちない。
その原因は、ひとことでいえば、これが藤堂志摩子自身の問題であるにもかかわらず、彼女の立場に立った視点が作中に無いからだ。
「チェリーブロッサム」は「銀杏(いちょう)のなかの桜」と「BGN(バックグラウンドノイズ)」の表裏二編で構成されている。だが、前者はあくまで二条乃梨子視点であり、後者は福沢祐巳のそれだ。
物語の構成としては適切であり、効果的である。だが、思えば志摩子の一人称という形式は過去の作品をみてもほとんど無く、「いとしき歳月(後編)」に収録されている「片手だけつないで」に佐藤聖と交代で用いられているのみだ。
そのせいで「マリアさまがみてる」全般において、志摩子をとりまく事情ばかりが一方的に語られ、我々は彼女の外周に感情移入せざるをえない。
また信仰という、例によって特殊な世界であるという距離感、およびその象徴とも言える志摩子の侵しがたい清らかさもあいまって、彼女の方の事情や心境はほとんどわからないのが現実だ。
というわけで、動機自体は、先の「白き花びらレビュー」と同様だが、信仰という観点から不完全ながら「チェリーブロッサム」に帰結する藤堂志摩子の内面、事情と心情の世界をなぞることで「そんなこと」の重さを量ってみたい。
このとき、彼女がどんな重圧のなかにいたのか。それは語ってみればやはり「なんだ、そんなこと」かもしれないが、それでも「ただ真面目で孝行者」と、度を越した生真面目さとして片づけられそうな志摩子の懊悩を、ちょっとでも弁護してあげたいのが本音のところである。
具体的に語られてない事情に関しては、例によって憶測にすぎず、またそれを断定的に書いている部分も多々ある。そこをだけは話はんぶんに、読んでみて欲しい。
志摩子の置かれている状況・彼女の覚悟
小学生のときキリスト教の信仰に目覚めた志摩子は、このときすでにシスターになることを決意している。
「十二になったら修道院にはいるから、勘当してほしい」と父親に話したというエピソードは衝撃的だ。
ここだけを見れば、それは幼い憧れの暴走かもしれないが、志摩子は今日にいたるまで、仮に11才で目覚めたとして6年もの間、それを抱き続けてきたことになる。
その原体験および、なぜキリスト教に目覚めたのかという出会いのエピソードは、久保栞同様に語られていない。志摩子自身うまく言えないのだろう。一般的にわかりやすく話せる劇的な出会いがあったわけではなく、季節をまって種子が芽吹くような自然さで、彼女は信仰を自らの根としたのかもしれない。
志摩子は物心がつくようになって、寺の娘という位置からその公言を抑えようとする。
もちろん、イスラム教などと違い、ましてや日本を生活圏として存在している宗教であれば、決して他の教えを受け入れて罪に問われるようなことはない。だが、志摩子はクリスチャンになることで、古い寺である実家に形にならないまでも様々な迷惑がかかることを想像し、それを回避したいと思った。
これが勘当を申し出た公的な理由だが、いまひとつ、彼女が自身の裡(うち)に持っていた決意があるように思える。
入信するということは、イエス様の言うことに対して、絶対的に貞淑な妻になるのと同じ意味がある。「あなたの色に染めてください」という結婚の決まり文句があるが、あれの一切妥協がないバージョンだ。シスターになり、イエス様の教えに身を捧げる以上、それ以外の価値観を裡に容れることはありえない。
信仰の究極をもとめ、愛する神様の前に一切の負い目無く立ちたいと願うとき、信仰が深ければ深いほど自己の内面に妥協を許すことはできないのだ。
少しくらい別の人の言うことを聞いたっていいんじゃないか、と思うひとも多いだろう。サンデークリスチャンと呼ばれる、毎週教会に通うだけのお気軽な信仰姿勢もある。だが、志摩子のように真剣な者にとってこれはまさしく婚姻と同じである。他の相手を同時に節操なく受け入れることはありえないのだ。
わかりやすく例えるなら、こころから愛し尊敬する人に料理をつくるとき、そこに少しでも異物が混入して溶けてしまったら、それを「まあ、これくらいべつにいいか」と思えるだろうか、ということである。はたから見た目には分からないかもしれないし、ひょっとすると食べるひとにも分からない程度のものかもしれない。だが、志摩子は絶対にそれができない娘なのだと思う。
そして志摩子の場合、異物と言ってはなんだが、その相手が自分の家という切ろうにも切れない縁にあることが問題だった。
だから志摩子は、両親に勘当を申し出る。自らの信仰を純粋に保持したいという出家としての行動であるが、迷惑がかからないようにという家族を思う心も動機だ。だが、結局彼女は両親に説得され、志摩子は中等部からリリアンに入学することになる。
信仰とは決まりを守るだけのことではないし、罪を犯したときの罰を恐れるこころでもない。
その本質は神に対する愛だ。恋愛の歌などが信仰にピタリとはまることがあるが、そういう意味でも「神様に恋をしている」というのが信仰状態を表すのに近いといえる。
志摩子は、一途に神様を愛している。
そして彼女にとって、恋し慕う神様の言うことは絶対だ。恋人の願いをきき、それを守って生活すること。そしてその中で神様の愛を感じるのが信仰者の喜びであり、生きる力なのだ。信仰者は、まるで神の愛を呼吸しているかのような生活をするようになる。
彼女はリリアン女学園ではじめてキリスト教的な生活を経験し、その呼吸を思い切りすることができるようになった。感動したことだろう。思い切り賛美歌を歌い、信仰を、神をイエスをマリアを愛していることを、堂々と宣言できる場所。キリストを賛美する時間が拡大する生活。彼女にとっての最初の解放。
だが、この生活のなかで家の事情を他に明かすことを、彼女は自らに禁じた。後にバレてしまうように、志摩子の父はさっさと賭事のネタにしてしまっているのがなんともいえないが、「古く大きな寺の娘が、キリスト教の信仰をもっている」ということがバレて家族に累が及ぶようなことになるなら、自分がリリアンからいなくなるという決意を、このとき彼女はすでにしている。
ここで志摩子の中に「リリアンで信仰的な生活をしたい」という希望と、「家のことがばれたらリリアンを去る」という戒律が同時に成立した。以後彼女は、リリアンに居続けるために、家のことを秘密にするようになる。
信仰、すなわち神の愛を呼吸して魂の息吹をつなぐようになった彼女にとって、それが専門的にできる唯一の場所がリリアン女学園だ。秘密が漏れだしリリアンを追われることは、植物が幹を切り倒されることに匹敵する。一度この素晴らしい世界を知ってしまった以上、信仰的な枯渇は死の苦しみだ。先の「神様に恋している」という表現を借りれば、それは遠くに引き裂かれることにも似ている。
これによって、志摩子はその心を他人に開かなくなった。堤防のように強固な壁をめぐらし、秘密に関しては水ももらさぬ覚悟で生活した。
しかし、防御壁を作ってしまった以上、常にあるのはいったい何処からこの堤が崩れるかわからないという恐怖である。
いつどこで嗅ぎつけられるかわからない。それゆえに誰にも話すことはなく、その対象にも志摩子はいっさい妥協しなかった。完全な遮断である。そここそが志摩子の生命線だからだ。相手がクリスチャンだとしても、信仰の友をつくることすらない。信仰という喜びのなかにあって、同時につねに怯えている彼女にとっては、こころを許した友こそが己の命を刈る者となりうるからだ。
そこに居ながらにして居場所を持たず、彼女はリリアンで怯えながら細々と生きてきた。決してみずから声を立てず、己に課した戒律によって自ら手足を縛り、口をつぐんで彼女は過ごしてきた。強制でも罰があるわけでもない。ここにいたいという、彼女自身の希望こそが戒(いまし)めの動機だ。
たとえ葉をもがれようと、枝を伐たれようと、幹を切り倒されようと、根さえあれば植物は生きていられる。志摩子が続けてきたのは、ただ根だけを命の根源とし、一切の陽光を避けて生き続けるという陰惨な歩みだった。だれとも枝を重ねることなく、だれとも葉を鳴らして語らうことなく、誰とも幹を並べることなく、そしてただ神様だけを愛す。
自ら枯れ木を装い、ただ信仰という根のみで、彼女は孤高に生き続けてきた。それは、乃梨子も例えていたように、地下活動しかできなかった隠れキリシタンを彷彿とさせる。
愛着と戒律の葛藤・聖との出会い
人間の消えた楽園に住みたい。
そう聖が漏らしたことがあるという。
居場所をうしなっていた志摩子にとって、聖はまるで同志のように思えていただろう。
ここにいてはいけない存在。孤高な生活。それは自分だけかと思っていたが、同じものを感じる人がいる。信仰をもつシスターや半端なクリスチャンもどきの学友にはなかった、はじめてリリアンで見つけた同類。心に闇をもつ同類であるがゆえに、こころを許したいと思った相手。背負っている荷をおろし、着ている甲冑を脱いで対面することのできたはじめてのひと。それが佐藤聖だった。
薔薇の館で手伝いをするうち、志摩子はそこに馴染み始める。
聖といっしょにいることで、孤独だった志摩子は救われるような思いだったろう。だが彼女は「一時の同情で助けるのは、かえって残酷ではないですか」と自らを猫にたとえて吐露する。
このときの志摩子に必要なものは、彼女の居場所だったというのが、おそらくは山百合会(一部除く)の見解だったろう。
志摩子はリリアンにいながらにして、居場所をもたないで来た。彼女自身が頑なに拒み続けてきたのだ。
祥子は志摩子に必要なものをこのとき見抜いている。「片手だけつないで」で志摩子を妹にしようとしたエピソードで示されている通りだ。
思えば「BGN」で志摩子の解放作戦を指揮したのは祥子である。紅薔薇は代々おせっかい焼きの家系、というよりは蓉子が不完全にしかできなかった聖の解放を、同じ「愛するものを奪われる」という白薔薇が宿命的にもっていそうな呪いから解き放つ使命を、祥子も継承しただけかもしれない。となればこれは見事に果たされたと言えよう。それはまだ先の話だが、まず聖の妹という居場所に志摩子を落ち着かせたのは、祥子の功績といえる。(もっとも、裏で蓉子が操っていたのかもしれないが)(というかむしろそんな気がするが)
紅薔薇の後押しもあったが、聖との絆によって志摩子はリリアンに、わけても山百合会に居場所を得た。
しかしそれでも「聖様のいないところにいる意味はない」と志摩子はいう。祐巳や由乃との友情を得ながらも、自らに課した「知られたら自主退学を」の戒律ゆえに決して心をひらかない志摩子である。
彼女は、無条件でつきあってくれるつぼみたちの友情に報いられないのが辛かったことだろう。
そして、誤魔化してきた愛着と戒律のせめぎ合いを発現させたのが、蟹名静のゆさぶりであった。
「白薔薇さま以外はお姉さまとよばない」とめずらしく志摩子が本音を吐いた選挙戦。
そしてバレンタインのデート。彼女の「中身をみるため」に、蟹名静が志摩子をゆさぶる。
準備の暇もあたえず廊下を走らされたり、あまりにも美しすぎるアヴェ・マリアに涙させられた。
志摩子の心の奥で沈殿していたものがかき乱され、信仰で誤魔化してきたものが表層に浮かび上がってくる。
それは「孤独」だ。
志摩子がもっともそれを感じたのは、静が去った後の、誰もいない学校だった。
蟹名静の手の込んだゆさぶりは、ここで志摩子の戒律が破られたときの状態を擬似的につくりあげている。
もし現実に志摩子がリリアン女学園から去らねばならないことになっていたら。
そのときの孤独が、ここに描かれているのだ。
途方もない孤独を体感する志摩子。
「大好きな人たちを失うのが怖かった」「一人になるのが怖かった」
それまで大切なひとを持たなかったからこそ耐えられた孤独。誰もいない学校は、逆に自分だけがいない学校を容易に想像させた。
もっとも、志摩子の秘密が明るみに出て本当にリリアンを去ることになったとしても、このときと同じようにかならず佐藤聖は志摩子の前にあらわれ、その孤独を癒しただろう。
愛するものを運命によって奪われるのは、白薔薇の伝統的な呪いなのかもしれない。
だが呪いがあったとしてそれは、志摩子の代で取り除かれたと思う。それがマリア祭の宗教裁判だった。
聖の卒業と、乃梨子との出会い
聖がいなくなったあと、志摩子は自分の存在をもてあましていた。
いつリリアンを去るやもしれず、ならば妹を持つことはないと、志摩子はそう思っていた。だが、愛された人間というのはある程度の水準でそれが満たされると、今度は愛されることではなく愛することで満たされるようになる。乃梨子と出会って志摩子は「楽しそう」だった。
志摩子はいままで悲壮な決意で秘密を隠し続けてきたせいか、他人に甘えるのが下手である。志摩子は、最初聖にすら秘密を明かすことをためらっていた。精神的に依存していた白薔薇ファミリーだが、それでも甘えるに甘えられない「お互いの秘密を知りながら尊重する」という距離がある。もっとも、甘えが苦手な志摩子にはいい距離感だったろう。
ところが、志摩子が甘えることのできない壁であるところの「秘密」を、あっさりと二条乃梨子は知ってしまう。
それは神様が導いた偶然だったかもしれない。唐突に秘密を知ってしまったという位置、志摩子のガード圏内にいきなり神様は乃梨子を割り込ませたのだ。状況が先につくられてしまったが、乃梨子こそが、志摩子の唯一甘えられる相手となったのである。
もしもの時はリリアンを辞すという志摩子の覚悟は揺らいではいない。だがそれでも、いままで聖を除いては、たった一人で偲んできた事情を共有できる人が現れた。これがどれくらい彼女を癒したかしれない。
もし、このアクシデントがなかったら、志摩子はずっと秘密を吐くことはできず、ましてや一度聖と分かちあってしまったという麻薬じみた解放感の記憶からずっと苦悶しただろう。
マリア祭での転機・志摩子の献身
「片手だけつないで」のころから志摩子を救いたいと思っていたであろう祥子が中心となって、彼女の秘密を公然と告白させるためのイベントが行われる。
もちろん志摩子と乃梨子の知らないところでだ。それだけにこのふたりにとって、共通の秘密を暴かれるのは極限状態そのものである。
瞳子に盗み出された数珠をキーアイテムとし、二人の薔薇さまを向こうに回して追いつめられる乃梨子。
祥子と令に乃梨子が詰問されているこのとき、志摩子のこころにはどんな想いがよぎっていただろう。
たぶん、乃梨子を助けるためには自分が告白するしかないと、聡明な彼女はすぐにわかったと思う。
乃梨子には、すでに自分の秘密のせいで累が及んでいるのだ。だれかに迷惑がかかるならリリアンから出ていく。何年も前からこの日の覚悟はできていた。中等部のころから頻繁にこうなることを考えていたのだ。いまさら命を惜しむような生半可な覚悟ではない。実際に志摩子は乃梨子が追い込まれたときに、彼女の手を握って下がらせ、自分が矢面に立っている。
このとき、志摩子が微かに笑ったという福沢祐巳の証言がある。
おそらくは一瞬の微笑。このとき、志摩子は覚悟を決めていたはずだ。
また戻るのだ。たった一人の信仰に。ただ神と自分だけの絆。それだけを胸に刻んで、それだけを頼りにいままで生きてきた。これはわたしだけの神。だれにも明かすことはない。明かしてはならず、明かす必要もない。だから私は誰にもこころをひらかない。
どうということはない。ただ、あの道にもどるだけ。自分一人しかいない孤高の道に。草も木も生えていない、冬の道に。
蟹名静がみせた、あの途方もない孤独に。
瞬間に、聖との絆が、祐巳や由乃、薔薇さまたちとの山百合会での想い出が、短かった乃梨子との楽しかった日々が脳裏に溢れ湧いた。振り返れば、それはまるで春のような暖かな日々だった。
このよろこびを知ってしまった彼女が、どれくらいそれを失うことを恐れていたか。
得てしまったからこそ、彼女は失うことを恐れていた。あのときの薔薇の館で、聖にすがってわんわん泣くほどに。
志摩子は、自分の価値をゼロだと思っている。
何ももたないがゆえに、神を感じることができ、それゆえに何もかもを得ている。彼女の信仰にのみ裏打ちされた精神の充足感はそこにある。
かつての彼女は、だから失うことをそれほど恐れなかった。
だが、いまの彼女は居場所を得た。得てしまったのだ。
信仰以外に何も持たなかった志摩子にとって、リリアンこそが、よろこびの全てだった。
決意の底流を轟々と流れ渦を巻く凄まじい葛藤。これでもう愛するものを失ってしまうのだという恐怖と絶望。およそ本能的とすら言えるそれら感情をねじ伏せて、志摩子は一歩前に出た。
リリアン女学園という世界で志摩子が得た、はじめての喜びの信仰生活。
まさか自分にこんなものが得られるなんて思ってなかった。
神様、ありがとうございました。
こころからの感謝とともなる、彼女の微笑み。
ただでさえ信仰しか持たない志摩子が、その報いや喜びの何もかもを捨てて乃梨子を護る。
このときの彼女は、およそ信仰者として完全に近い状態だったろう。
極限まで削り落とされた、信仰に付随する現世的なよろこび。
残ったものは一切の不純物を包含しない美しい金属のような信仰心。
そして告白。
あれほど露見を恐れてきた秘密を、ついに志摩子は自ら告白する。
自刃も同然のその言葉に、乃梨子はその場でへたり込んでしまった。
だが、その目に映るのは神々しい志摩子の姿。清らかな信仰心そのもののような志摩子。その姿は、信仰にさして興味もないであろう祐巳と乃梨子をして「言葉で言い表せないほどきれいだった」と言わせている。自分を捨てて何かを得た者の顔が、そこにあった。
後悔などあろうはずがない。すべてを感謝して告白を果たした志摩子が乃梨子に歩み寄る。
彼女と視線を結んだ瞬間に、抱きついて子供のように泣く乃梨子。
彼女とともに、このとき多くの生徒が「一大巨編の感動ドラマでも観たように」涙を流したという。だが、もし現実に目の前でこんなイベントがあったとして、外面だけ見ている人間が、はたして泣いてしまうようなことがあるだろうか。事実、わけも分からずに泣いたと乃梨子も祐巳も言っている。
この理由は、志摩子の神々しさがこのときの場を圧倒していたからだろう。その場にいなければ感じ取れなかったであろう志摩子の悲壮な、しかしこれしかないという決意。それが彼女から乃梨子へ流れた瞬間に、その場にいた全員に展開したのだ。状況をわかって泣いた人間などほとんどいまい。多少でも関わった祐巳がボロボロなけてしまうのも道理である。
それだけに、いままでの志摩子をみつめてきた神様だって、感動して泣いたに違いない。
志摩子と乃梨子にとってはまるで奇跡のように、リリアンを退学しなくてはならないという状況がひっくり返される。
そして、万雷の拍手に祝福される二人。
斜めからみれば、見た目は悪質な「ドッキリ」のようだったマリア祭は、こうして終わった。
帰結
志摩子の告白は感動的だった。だがこれは結局、いびつな信仰である。
あまりに真面目で純粋であるがゆえに、悩みねじくれてしまった信仰。孤独であるが故に志摩子と神との繋がりは強固なものとなった。だが、クリスチャンは修行僧ではない。神の代理として隣人を愛するのがキリスト教の本質だ。回り道をしてしまった志摩子は、ようやくそこに戻ってこられたのだと思う。
「マリア祭の宗教裁判」によって彼女が得たものを、解放、と一言で言ってしまっていいものだろうか。
結論を言ってしまえば、彼女は信仰以外のなにもかもを捨てたことと、友の支えのおかげで、あたらしく生まれ変わることができたのだと思う。
いままでは異物の混入を怖れていた。そして「信仰」を自分とは別のものとして、手で抱くようにして守っていたのだ。
だがこの事件により、彼女は自分を捨てることで逆に信仰を自分のものにし、自己を確立できたのだと思う。
エピソードの最後で、志摩子は乃梨子を仏像見物に誘っている。
家が仏教の寺であろうが関係なく、自身のなかに揺るぎない信仰を内包した藤堂志摩子というひとつの個性がこのとき誕生していたのだ。
ふっと消えてしまいそうな儚げなマリア様は、実体として安定した存在になった。
いままで苦しんだね。よかったね。もう日の光をあびていい。枝を葉を茂らせていい。友達を愛していいんだよ。
神様もそう思っていただろう。自分を慕うあまり、自らを縛り続けてきた愛すべき娘のことを。
余談・これからの志摩子
ところで、この時期に大がかりな舞台を用意した山百合会には心から感謝したい。
これが単に「みんなしってるよ?」と軽い無責任さでバレたのでなくて本当に良かった。
そのときこそ、彼女はグチャグチャに混乱してしまっただろう。体育祭で自分の親父が飛び出してきたのをいきなり目撃していたら志摩子はゲシュタルト崩壊くらい起こしていたかもしれれないし、文机のなかから自分が競走馬あつかいされてる配当表(しかもコピー用紙)などみつけでもしたらその場で塩の柱になっていたか、今度はヒンズー教あたりに転身したかもしれないからだ。
さて今後の展開だが、この事件以後の志摩子は、本来はひと味ちがっているはずだと思う。
自らを解放させた志摩子。これからはその本性がでてくるはずだ。
ただそれはできれば、姉に甘えることで解放されていくべきものだったとおもう。
とはいえ、闇を払えた志摩子は、絆は残るが聖と惹かれあうことはないかもしれない。
乃梨子を愛する生活のなかで、志摩子は本当の意味で徐々に解放されていくだろう。
姉として妹を愛するという体裁をとった攻撃的な甘え。
これが志摩子には必要なことだと思う。甘えが下手くそな彼女には大変なことかと思うが、頑張って欲しい。
もっとも、度を越して聖の祐巳に対するレベルにまでイッしまってはちょっとどうかと思うが。
ついでに余談だしこんなことを筆者は望んでいないが、物語の王道ならばこのとき、志摩子はここでこそ信仰の道に目覚めて修道院に入ってしまうと思う。
リリアンから出て行かざるを得なかったのではなく、自らリリアンで必要な変革と成長を勝ち取ったゆえのステップアップとして。
まあ、それはともかく。
すでに何度か目の再読を行っているが、「チェリーブロッサム」以後の作中では、あまり志摩子の内面が描かれるようなエピソードがない。
彼女には、なんというか、事情が許されるようになったので公言できるようになったという程度の変化しかないように思える。
慣れない自由をもてあましているのかもしれないが、今後、本来的に志摩子らしい側面が描かれることを期待している。
あとがき
ずいぶん長い文章になってしまってます。
でも、これが書き上がってやっと「藤堂志摩子」という人物が理解できたように思えました。
実際にそれぞれの局面で志摩子さまがここまで考えていたのか、と問われれば答えは当然、否だと思います。
彼女はこんなふうに大げさに叫ぶことも、自分の感情を事細かに分析することもないでしょう。
リリアン退学がかかっている局面で乃梨子を庇ったときの心境をどんなに追求しても、志摩子さまはただ「どうしてかわからない」とだけ言うのだと思います。でもそこにはきっと「イエズス様ならこうするとおもったから」という満足げな笑みが浮かぶのではないでしょうか。
「信仰以外になにももっていない」という表現にもやや問題はあって、厳密には生命以外のなにももっていないという状態をさすのでしょう。彼女には美貌も、大きな家も、不自由のない暮らしもあるのです。
でも、志摩子さまはそれに執着していない。たぶん、捨てる必要があれば捨ててしまえるのだと思います。
ただ、そのなかでどうしても捨てられないものが、リリアンでの生活だったのではないか。
そしてそれを捧げるという試練。それなくしてなかった超越。これが「チェリーブロッサム」までの筋だったように思えます。